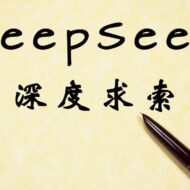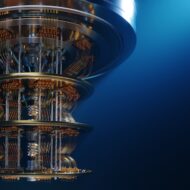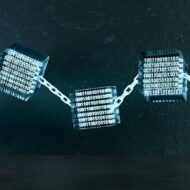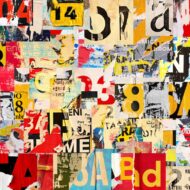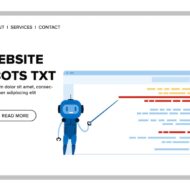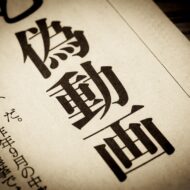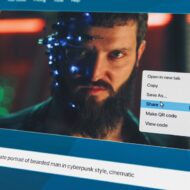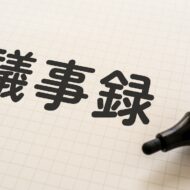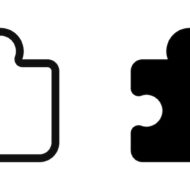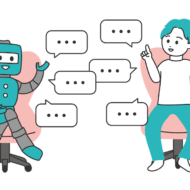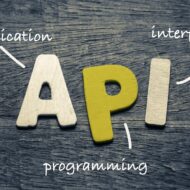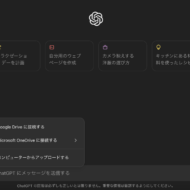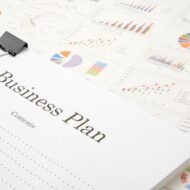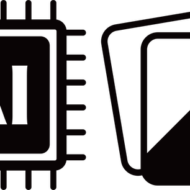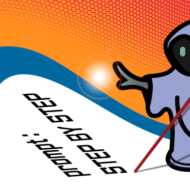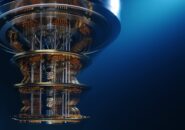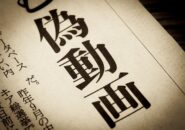近年、生成AI(人工知能)の技術は驚異的な進化を遂げ、その応用範囲もますます広がっています。しかし、その進化と共に生じる法的・倫理的な問題に対処するために、規制の必要性が急激に高まっています。
本記事では、特に日本において生成AIの規制はどのような現状にあるのか、そして今後どのような方向性が示されるのか、解説していきます。
生成AI規制、日本は緩い?現状を解説
日本における生成AIの規制は、今までは比較的緩やかなものとされていましたが、現在以下のような問題が浮上しています。まず、生成AIによって作成されたコンテンツに関する著作権の問題です。日本の著作権法では、著作者は人間でなければならず、AIが作成したコンテンツの著作権は明確ではありません。このため、AIによって生成された楽曲や美術作品などの著作権の帰属は不透明なままとなっています。
また、生成AIを利用した偽の情報や人権侵害など、その悪用による社会問題も懸念されています。しかし、これらの問題に対する具体的な規制や法律は十分に整備されていないのが現状です。
一方で、日本政府はAIの活用を推進しており、2020年に策定された「人工知能社会基本戦略」では、AI技術の発展と利用を積極的に支援する方針が掲げられています。このため、矛盾を孕むようですが、現状では生成AIに対する規制は緩やかなものとなっているのです。
世界の生成AI規制状況を解説
世界各国における生成AIの規制は、その歴史を通じて様々な変革を経験してきました。以下では、各国の対策の変革の歴史を具体例とともに触れ、その背景や影響について解説します。
欧州連合(EU)
EUは、AIの倫理的な使用と透明性を重視した規制を進めています。2021年に発表された「AI法規制提案」はその一環であり、AIシステムのリスク管理や透明性の確保が求められています。これにより、個人の権利保護や公正な取引環境の確保が図られ、ヨーロッパ全体でAI技術の安全性と信頼性が向上しています。
アメリカ
アメリカは、AI技術の研究と開発を積極的に支援する一方で、規制は比較的緩やかなものとなっています。しかし、過去にはAIによる個人情報の収集や悪用に対する懸念が高まり、それに対応する法律の制定や規制の強化が行われてきました。例えば、2018年のカリフォルニア州の「消費者プライバシー法(CCPA)」は、個人のプライバシー保護を目的とした法律であり、AI技術の利用に関する規制も含まれています。
中国
中国は、AI技術の急速な発展とその悪用への懸念から、すでに厳格な規制を導入しています。2021年に発表された「データセキュリティ法」では、AI技術の利用に関する規制が強化され、個人情報の保護や国家安全保障の観点から、AI技術の利用に制限が設けられました。これにより、個人情報の流出や悪用に対するリスクが低減し、国家の安全保障が強化されることが期待されています。
世界各国における生成AIの規制は、その背景や文化、社会的な価値観に応じて異なる歴史を持ちます。しかし、AI技術の進化に伴い、それに対する規制の必要性がますます高まっており、国際社会での協力や知識の共有が重要となっています。
日本での規制の今後を予測
日本における生成AIの規制は、今後ますます強化されると予想されます。特に以下の点が重要なポイントとなることが推測されます。
著作権の問題に対する規制強化
日本では現状、AIが生成した楽曲や美術作品などの著作権の帰属が不透明なままですが、今後は、AIによって生成されたコンテンツの著作権を明確化する法律や規制の整備が進むことが予測されます。具体的には、AIの生成するコンテンツについて著作権が発生する条件や権利の保護方法について、新たな法律が制定される可能性が挙げられます。これにより、著作権侵害や紛争の解決がスムーズになり、AIを活用したコンテンツの安定した利用が促進されるでしょう。
AIの悪用に対する法的対応の強化
AIの悪用による社会問題への対応も今後強化されることが予測されます。偽の情報や人権侵害など、生成AIの悪用に対する具体的な法的対応が必要です。これには、法律の改正や新たな規制の導入が含まれる可能性があります。例えば、AIによる個人情報の収集や悪用に対する厳しい規制が導入されることで、個人のプライバシーや権利の保護が強化されるでしょう。
倫理委員会の設立とAI倫理規範の制定
日本では、AI技術の倫理的な使用に関する規範や指針が整備されることが期待されます。政府や業界団体が主導して倫理委員会が設立され、AI倫理規範の制定や運用が行われる可能性があります。これにより、AIの開発や利用における倫理的な基準が明確化され、社会全体でのAI技術の健全な発展が促進されるでしょう。
国際的な規制との連携と調整
日本の規制が国際的な規制と連携し、調整されることも重要です。世界各国が独自の規制を進める中で、国際的な標準やルールの整備が必要になります。日本は国際社会での協力や情報共有を通じて、AI技術の安全性や信頼性の向上に努めることが予測されます。これにより、国際的な規制の一貫性が確保され、グローバルなAI技術の利用が促進されることが考えられます。
まとめ
現在、日本における生成AIの規制は現在比較的緩やかな状況にありますが、今後は著作権や社会問題への対応を強化する方向に進むことが予想されます。生成AIの技術が進化する中、法的な枠組みの整備が不可欠であり、安全で信頼性の高いAIの普及に向けた取り組みが重要となります。